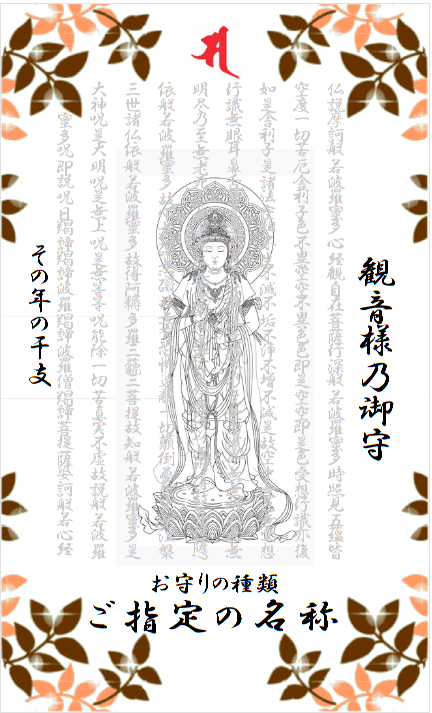【PR】劇的に金運が上がるお守りとは
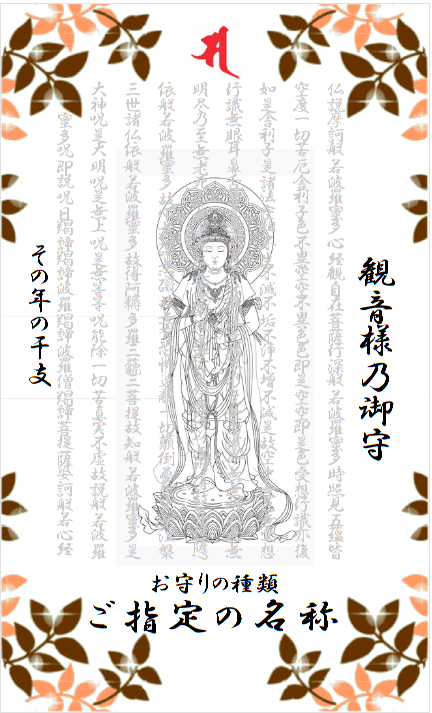
はじめに
明治神宮は東京都渋谷区に位置する、日本を代表する神社の一つです。観光地としてだけでなく、初詣の参拝者数が全国で最も多い神社としても知られています。その明治神宮では、参拝者の祈りや願いを形にした「お守り」が多数授与されています。
本記事ではスピリチュアル的な解釈を排し、実際の授与品としてのお守りの種類・特徴・受け方・扱い方を、事実ベースで詳しく紹介します。
明治神宮のお守りとは
お守りは神社で授与される護符の一種で、参拝者が自分や家族を守るために身につけるものです。明治神宮におけるお守りは、単なる記念品ではなく「神前にて祈願を受けた授与品」として扱われます。
明治神宮には複数の形式があり、「御守(おまもり)」「守札(しゅさつ)」「神符(しんぷ)」などに分類されます。御守は携帯型、守札は持ち歩き型の札、神符は家庭内に祀る形式のお札です。いずれも購入というより「初穂料を納めてお受けする」という形が正式です。
授与所は境内の複数箇所に設けられており、主に長殿、神楽殿、南授与所で受け取ることができます。授与時間は季節や行事により変動するため、参拝前に明治神宮公式サイトで最新情報を確認するのがおすすめです。
主なお守りの種類と特徴
心身健全守
最も一般的な明治神宮のお守りで、身体と心の健康を祈る「心身健全守」は、男女問わず人気があります。朱色と紺色の2色があり、いずれも小型で持ち歩きやすい布製。通勤バッグや財布の中に入れる人も多く、家族への贈り物としても選ばれています。
平型守
紙のように薄い形状をしたお守りで、財布や定期入れなどに入れてもかさばりません。軽量で携帯性に優れているため、仕事中や外出時でも自然に持ち歩けます。デザインは落ち着いており、年齢を問わず持ちやすいのが特徴です。
除災招福守
旧南参道鳥居に使われていた台湾檜の木材を再利用して作られた特別なお守りです。「災いを除き福を招く」という願意を込めて作られ、木の温もりと香りを感じられます。自然素材を活かした質感は他に類を見ず、参拝記念としても人気があります。
学業成就守・合格守
受験生や資格試験を控える人に授与されるお守りで、努力が実を結ぶよう祈念されています。明治神宮では、学業成就と合格守が別々に用意されており、勉強の継続や集中力維持を願う人が多く受け取っています。
就職成就守
就職活動を控える学生や転職を考える社会人に向けたお守りです。自分の実力を発揮できるよう祈願されたもので、内定や昇進を祈る人に選ばれています。
縁結び守
恋愛成就だけでなく、人間関係全般の良縁を願うお守りです。明治神宮では「相和守(あいわまもり)」という夫婦円満のためのお守りもあり、楠の香りがしみ込ませてあるのが特徴です。
勝守
スポーツや試験、仕事での勝負ごとなど、自分の力を最大限に発揮したい場面に向くお守りです。「勝つ」ことよりも「努力を成し遂げる」意味を重んじる人に好まれます。
病気平癒守
病気やけがの回復を祈願したお守りで、本人が持つだけでなく、病床の家族や友人に贈ることも多い授与品です。白や淡い色合いの清楚な布地が特徴です。
安産守・赤ちゃん守
妊婦やその家族に人気のあるお守りで、無事な出産と母子の健康を祈願します。参拝時にいただく人も多く、出産後は感謝を込めて返納するのが一般的です。
開運守
日常生活全般に幸福が訪れるよう祈るお守りで、どの年代にも人気があります。特定の目的がない場合や、初めてお守りを受ける際に選びやすい万能型といえます。
特別な授与品:開運木鈴「こだま」
明治神宮の境内で自然倒木や損傷を受けた御神木を再利用して作られた丸い木製の鈴「こだま」は、明治神宮らしい自然との共生を象徴する授与品です。手に取ると温かみがあり、振ると木ならではの柔らかい音が響きます。お守りとしてもお土産としても人気で、数量が限られているため早い時間に授与所を訪れる人も多いようです。
授与場所と初穂料
お守りは主に「長殿」「神楽殿」「南授与所」で授与されています。どの授与所も境内中心部にあり、参拝後に立ち寄りやすい場所です。授与品の種類によっては一部の授与所でのみ取り扱っているものもあります。
初穂料(いわゆる価格)はおおむね1000円前後が中心ですが、木製の除災招福守や特別記念のお守りなどはもう少し高めの設定です。購入ではなく「お受けする」という表現が正しく、金額に見合うというより「感謝を捧げる」意味合いで納めます。
お守りの扱い方と注意点
お守りを受けたら、袋を開けずにそのまま身近に持ち歩くのが基本です。中身には神符が入っており、開封するとその役割が失われるとされています。汚れた場合は水で洗わず、柔らかい布で軽く拭う程度にします。
また、お守りは一年を目安に新しいものに替えるとよいとされています。古いお守りはそのまま捨てず、明治神宮の古神符納所に返納しましょう。境内の返納所では、燃やして清める「お焚き上げ」が行われます。
旅行や引っ越しなどで返納できない場合は、近くの神社で相談しても構いません。ほとんどの神社では、他社で授与されたお守りでも丁寧に納めてくれます。
お守りを選ぶ際のポイント
まず、自分の目的を明確にすることが大切です。健康・学業・仕事・家庭など、何を願いたいのかを決めたうえで対応するお守りを選ぶと良いでしょう。
形状にも注目すると扱いやすさが変わります。常に携帯したいなら薄型の平守、室内で祀りたいなら神符、日常的に見える場所につけたいなら鈴型など、用途に合わせて選びましょう。
また、素材やデザインにも意味が込められていることがあります。旧鳥居材や御神木など、神社の歴史や自然と関わりを持つお守りは、記念としての価値も高いものです。自分が「心地よい」と感じるものを選ぶことが、長く大切にできる秘訣です。
まとめ
明治神宮のお守りは、参拝者の願いを静かに支える存在です。種類が豊富で、健康・学業・縁結び・開運など、目的に応じて選べます。見た目の華やかさよりも、「どういう想いで受けるか」を意識することで、お守りはより身近な存在になります。
お守りを受けたあとも、年に一度は参拝し、新しいものに取り替えることで気持ちを新たにできます。境内には古神符納所も設けられているため、安心して返納が可能です。
注意:本記事の情報に誤りが含まれる可能性がありますので、正確な内容を知るには必ずご自身でご確認ください。
【PR】劇的に金運が上がるお守りとは